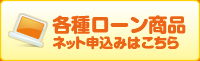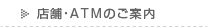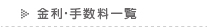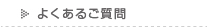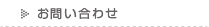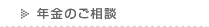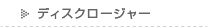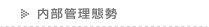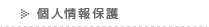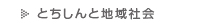|
●「地域密着型金融推進計画」について
|
|
当金庫は、地域の取引先顧客との良好な信頼関係を築き、長い期間維持し、地域社会との「共存共栄」を図ることを経営理念に掲げ金庫経営を行ってまいりました。日々の取引を通じて顧客ひとり一人の顔が見え、ニーズをよく理解し、心を通わすことによって様々な情報を得、それらを活かした各種金融サービスの提供を実施し、地域社会の発展に寄与しております。また、当金庫自身の経営体力の維持・増強が、リスクテイク可能な融資行動に直結し、地域の利用者の利便性向上に結びつくとの認識から、収益性の向上、財務の健全性確保、経営基盤の強化、などに資する諸施策を積極的に実施しております。 こうした状況下、平成16年12月に、金融庁より「金融改革プログラム-金融サービス立国への挑戦-」が公表されました。 当金庫としては、地域社会活性化のために質の高い金融サービスを提供し続ける役割の大きさを改めて確認するとともに、「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム(17~18年度)」に掲げられた多くの経営課題に積極的に取組むこととし、2年間の「重点強化期間」において実施する具体的施策、施策達成のための取組みを栃木信用金庫の「地域密着型金融推進計画」として次のとおり定めました。 ●「地域密着型金融推進計画」 当金庫の推進計画 ・対外的な目標である中小企業の再生支援・地域活性化と対内的な目標である収益性の向上、財務の更なる健全化、ガバナンスの向上をバランス良く達成するため、以下の項目について積極的に取組みます。 1.事業再生・中小企業金融の円滑化 (1)創業・新事業支援機能等の強化 ・企業の将来性や技術力を的確に評価できる人材の養成に注力し、定量面と定性面のバランスのとれた審査能力の定着を図る。 ・審査態勢の強化策として17年4月より融資審査部を設置し、管理部門を分離しました。特定業種については6ヶ月毎に担当者のローテーションを実施し、幅広い業種の特性や審査能力の取得を図る。 ・中小企業が有する知的財産権・技術の評価や発掘等に関して県内の大学とネットワークを構築し、活用する。 ・日本政策投資銀行、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫等との情報共有と協調投融資等の連携強化を図る。 (2)取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 ・中小企業の成長機会の把握・実現に資するため、中小企業に対するコンサルティング機能及び情報提供機能の一層の強化など、取引先企業に対する経営相談・支援の強化に向けた取組みを行う。また、M&Aの仲介業務運営に向け態勢整備をし運用を開始する。 ・経営支援チームの所属組織の改変を行うことで組織的取組態勢を強化し、従来の健全債権化への取組みの継続強化を図る。 ・営業店のモニタリング機能強化等により、より踏込んだ実態の把握と経営改善の支援を行うとともに、早期の対応を取る事で不良債権の新規発生防止と管理態勢強化を図り、改善取組対象先について10%のランクアップを目指す。 ・経営支援等の実績に関する情報開示は、できるだけ具体性のある形で公表できるよう拡充を検討していく。 (3)事業再生に向けた積極的取組み ・取組み態勢の強化を図るため、17年4月より融資管理部を新設し、従来の「経営支援チーム」3名と債権管理担当2名との5名体制とした。経営支援と債権管理を連携させることにより、リスク管理債権の減少に対する認識強化を図り、一層の踏込んだ活動を展開する。 ・再生支援実績に関する情報開示は、できるだけ具体性のある形で公表できるよう検討することとし、再生実績については、ノウハウの共有化等が図れるよう業界団体のの要請には積極的に応えるよう対応する。 (4)担保・保証に過度に依存しない融資の推進等 ・融資審査の取組みにあたっては、キャッシュフローを重視した態勢で臨むほか、企業の自己資本比率、キャッシュフローによる償還年数、インタレスト・ガバレッジレシオ等の計数を財務制限条項として活用し、企業の将来性や技術力を的確に評価できる態勢を強化する。 ・「しんきん信用リスクデータベース」を審査業務と新金利体系に反映させる。 ・ノンリコースローンやプロジェクトファイナンスの検討を行う。 ・無担保を原則とした低利な貸出制度を創設する。 (5)顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化 ・「与信取引に関する顧客への説明態勢に係るマニュアル」を制定する。 ・営業店における顧客への感度を高め、小さな苦情についても記録に留めることを徹底する。 ・蓄積された苦情情報については、データベース化し発生原因別に分類・分析を加えて営業店に情報をフィードバックする。 (6)人材の育成 ・業界団体主催の「目利き力養成講座」・「再生支援講座」・「業種別企業診断講座」等に積極的に参加する。各営業店と融資審査部・融資管理部において、15年度以降の本講座受講者を2名以上配置を目標とする。 ・中小企業の将来性や技術力を的確に見極める人材を育てるため中小企業診断士を2年内に1名(現在、中小企業診断士養成課程に派遣中の者を除く)輩出を目標とする。 ・取引先企業の活性化を支援する経営体制を強化するため2級FP技能士(現在34名、全職員の12%)を各営業店2名配置(窓口及び渉外担当者)より、資格取得者50名(全職員の18%)を目標とする。 ・宅地建物取引主任者資格取得者を(現在18名、全職員の6.3%)各営業店1名配置より、資格取得者25名(全職員の9.5%)を目標とする。 2.経営力の強化 (1)リスク管理態勢の充実 ・新BIS規制下のリスク管理態勢の基本的な考え方の習得を主な方針としバンキング勘定全体のリスク管理態勢の構築と「アウトライヤー銀行」のストレステストの測定方法の確立を図ることを目標とする。 (2)収益管理態勢の整備と収益力の向上 ・短期プライムレートの算定は「調達金利+経費率+目標収益率」により算定し、長期プライムレートはこれに0.3%加算して運用する。個別の融資案件については、格付け、融資期間及び取引先の保全率に応じた上乗せ利率を採用し、貸出金の摘要利率とする。 ・「しんきん信用リスクデータベースシステム」の積極的な利用により、格付けに基づいた金利上乗せ幅の妥当性の検証を実施する。 (3)ガバナンスの強化 ・全国信用金庫協会が検討を加えている業界としての取組み策・方針を踏まえた情報開示の内容・開示方法を実践する。 ・地区ごとに(仮)決算説明会を実施し、一般の会員からの意見を収集し、それらの意見を総代会で紹介していく。 ・一般の会員からの意見をより多く収集する手段として、ミニディスクロージャー誌の中にアンケートを盛込んで配布することを検討する。 ・総代会や決算説明会等において、金庫の経営計画(本部の具体的施策等)を伝えていくよう検討する。 (4)法令等遵守(コンプライアンス)態勢の強化 ・法令等遵守態勢の強化策として、コンプライアンス諸規程、不祥事件取扱に関する規程、コンプライアンスマニュアル、参考資料等を用いた階層別研修・各部店単位の勉強会を積極的に取組み、不祥事件等の発生の未然防止を図る。 ・個人情報等情報保護諸規定のより一層適切な管理・取扱の確保をするとともに、個人情報保有リスクの削減のための、保有する個人情報の削減と管理方法の一元化を図る。 ・コンプライアンス・ホットラインの案内掲示方法の改善を図る。 (5)ITの戦略的活用 ・「とちしんネット」を中心とした情報システムの高度化を図り、地域における顧客満足度NO1を目指し当庫のオリジナリティーを活かしたCRMシステムを構築するとともに、ALMシステム等高度なリスク管理手法の積極的な導入・利用を推進し、安心して取引できる金融機関としての評価を堅持する。 ・市場リスク管理の高度化を図るため、VAR手法を前提に検討を進め、導入に必要な関連システムの整備及び対応スタッフの養成を行う。 ・IT投資の客観的な検証が行えるよう事務量の把握、事務フローの見直し、事務スキルの評価、顧客満足度の調査等関連業務の定量化を検討する。 (6)協同組織金融機関の市場リスク管理態勢の強化 ・新BIS規制下の市場リスク管理態勢の基本的な考え方と体制整備の構築並びに「アウトライヤー銀行」のストレステストの測定方法(市場リスク感応度資産)の確立を目標とする。 3.地域の利用者の利便性向上 (1)地域貢献等に関する情報開示 ・地域の中小企業に対する資金供給状況及び当金庫利用者に対する預金の地域貢献状況をディスクロージャー誌への掲載及びホームページで公開する。 ・利用者からの頻度の高い質問・相談に対する回答事例を作成しホームページ等で公表する。 (2)地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立 ・「おもてなしの心」をもってお客さまのニーズにお応えする積極的なサービスの向上を図り、「一番近くの親しみやすい」、「一番安心して預けられる」、「一番相談しやすい。借りやすい」「一番便利で行きやすい」地域ナンバー1の店づくりを構築する。 ・地域の特性等を踏まえた利用者満足度アンケート調査等の結果発表を経営方針へ反映する。 ・研修の実施により接客技能の向上を図る。 (3)地域再生推進のための各種施策との連携等 ・地域(栃木市内、栃木市外、宇都宮地区)におけるPFⅠへの取組みを支援する。 ・地方公共団体、商工団体との連携を強化する。 ・地域経済活性化に向けた地域と一体となった取組み推進を行い、当金庫のネットワークを活かした情報の収集・提供を行っていく。 4.進捗状況の公表 ・当金庫ホームページ及びディスクロージャー誌にて進捗状況を公表する。 ・「金融改革プログラム推進委員会」において毎月1回進捗状況をチェックし、役員会(毎月開催)及び理事会(偶数月開催)に報告する。 推進計画数値 |
| 項 目 | 17年3月期実績 | 2年後の姿 |
|
コア業務純益 |
733百万円 | 900百万円 |
|
自己資本比率 |
7.20% | 7%台 |
|
不良債権比率 |
13.05% | 6%台 |
| 私的整理ガイドライン及び外部機関の事業再生機能を活用した再生企業数 | 9社 | 20社以上 |
| 中小企業診断士・宅地建物取引主任者・2級FP技能士資格者等数 | 57名 |
全職員の30%に相当 84名 |
| 戻る |